×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
前のPCで使っていたTVチューナー付キャプチャーカードも挿してみた。
パソコンの設置場所を変えたので、ビデオ入力の環境があるメインPCに移動。
KWORLD製 VS-MCE201
http://www.keian.co.jp/products/products_info/vs_mce201/vs_mce201.html

2007年に4千円くらいで購入。
内蔵チューナーの質が悪いので、外部入力専用。 タイマー予約機能は試したことがないや。
購入後1年くらいはそこそこ録画もしていたけれど、最近は休眠中。
結局はPCで録画中は何も出来ないし。
家電の方が遙かに楽だし、安いし、変なトラブルも失敗も無い。
テレビを見るだけならMPC-HCの「deviceを開く」で視聴可能。
VLCでは、なぜか緑色になってしまう。
録画は、付属の「InterVideo HomeTheater」が手っ取り早い。
あまりに低機能というか単機能すぎるけど安定してる。
「ふぬああ」ことhunuaaCapは素人お断りな使いにくさだけど、まぁ高機能。
しかし設定だけで疲れてしまい、結局使わないままだな。
「ふぬああ」はコーディックを選ぶ感じ。 圧縮率を低くすれば問題ないけれど、だったら付属ソフトで充分かな、という流れ。
KMPlayer でもキャプチャー可能。 最新バージョンは最初から日本語対応。
ちょっと重いけれど使いやすい。 設定も「ふぬああ」に比べれば格段に楽だけど、なぜかキャプチャに失敗することもある。
それにしても……
最近はPCでAMラジオの録音もやっている。 ラジオのヘッドフォン端子をPCのlineINに繋いで録音。
実は古いラジカセのタイマーの使い方を忘れちゃったので、非常用のつもりだった(爆)
まぁ、いまさらカセットテープというのもアレだし、何よりもPCのデータにすると倍速(以上)再生とか、巻き戻し・早送りの再生が簡単だ。
USB接続のラジオとか、USBに録音できるラジカセ・ミニコンポも考えたけれど、AM録音のためにわざわざ買うのも、もったいない気がした。
ソフトは Recky(フリー)を使用。
モニタも出来るし、レベル調整もお任せ出来るので便利。
Recky - スカパー STAR digio(スターデジオ)の録音に最適なパソコン用録音ソフト
http://www.recky.gotdns.com/ver1/index.html
手軽に録音するときは ALSong も使う。
歌詞表示やアルバム作りにも対応した多機能MP3プレーヤー、ALSong
http://www.altools.jp/product/alsong/intro.aspx
「手軽」といっても、事前の設定でちょっと迷った。
サウンドカード増設した後は、これらの設定が若干煩雑になっちゃってるな。
一度設定が出来てしまえば問題ないけれど、微妙に敷居が高いかも。
サウンドカードとビデオキャプチャボードを挿したら、PCの雑音電波レベルが大きくなった模様。
100均の延長コードで、ラジオをパソコンから遠ざけなきゃいけなくなった。
ちなみに…
増設したビデオカードはTV出力が可能。
黒赤緑の謎のコネクタケーブルは、黒がビデオ出力だった。
なんちゅうか、いつのまにかマルチメディア(死語)なPCになってしまっているなぁ。
パソコンの設置場所を変えたので、ビデオ入力の環境があるメインPCに移動。
KWORLD製 VS-MCE201
http://www.keian.co.jp/products/products_info/vs_mce201/vs_mce201.html
2007年に4千円くらいで購入。
内蔵チューナーの質が悪いので、外部入力専用。 タイマー予約機能は試したことがないや。
購入後1年くらいはそこそこ録画もしていたけれど、最近は休眠中。
結局はPCで録画中は何も出来ないし。
家電の方が遙かに楽だし、安いし、変なトラブルも失敗も無い。
テレビを見るだけならMPC-HCの「deviceを開く」で視聴可能。
VLCでは、なぜか緑色になってしまう。
録画は、付属の「InterVideo HomeTheater」が手っ取り早い。
あまりに低機能というか単機能すぎるけど安定してる。
「ふぬああ」ことhunuaaCapは素人お断りな使いにくさだけど、まぁ高機能。
しかし設定だけで疲れてしまい、結局使わないままだな。
「ふぬああ」はコーディックを選ぶ感じ。 圧縮率を低くすれば問題ないけれど、だったら付属ソフトで充分かな、という流れ。
KMPlayer でもキャプチャー可能。 最新バージョンは最初から日本語対応。
ちょっと重いけれど使いやすい。 設定も「ふぬああ」に比べれば格段に楽だけど、なぜかキャプチャに失敗することもある。
それにしても……
最近はPCでAMラジオの録音もやっている。 ラジオのヘッドフォン端子をPCのlineINに繋いで録音。
実は古いラジカセのタイマーの使い方を忘れちゃったので、非常用のつもりだった(爆)
まぁ、いまさらカセットテープというのもアレだし、何よりもPCのデータにすると倍速(以上)再生とか、巻き戻し・早送りの再生が簡単だ。
USB接続のラジオとか、USBに録音できるラジカセ・ミニコンポも考えたけれど、AM録音のためにわざわざ買うのも、もったいない気がした。
ソフトは Recky(フリー)を使用。
モニタも出来るし、レベル調整もお任せ出来るので便利。
Recky - スカパー STAR digio(スターデジオ)の録音に最適なパソコン用録音ソフト
http://www.recky.gotdns.com/ver1/index.html
手軽に録音するときは ALSong も使う。
歌詞表示やアルバム作りにも対応した多機能MP3プレーヤー、ALSong
http://www.altools.jp/product/alsong/intro.aspx
「手軽」といっても、事前の設定でちょっと迷った。
コントロールパネルから「サウンドとオーディオデバイス」を開く。
「規定のデバイス」で、ちゃんと設定。 拡張ボードさしてなきゃ、表示されるのはオンボードのリアパネルのlineかフロントのマイクだけのはず。
「詳細設定」を開き、そこでも設定を確認。 ちゃんと設定したはずなのに、なぜか再起動後とか、他のソフト使用後に設定が変えられてる時がある模様。
サウンドカード増設した後は、これらの設定が若干煩雑になっちゃってるな。
一度設定が出来てしまえば問題ないけれど、微妙に敷居が高いかも。
サウンドカードとビデオキャプチャボードを挿したら、PCの雑音電波レベルが大きくなった模様。
100均の延長コードで、ラジオをパソコンから遠ざけなきゃいけなくなった。
ちなみに…
増設したビデオカードはTV出力が可能。
黒赤緑の謎のコネクタケーブルは、黒がビデオ出力だった。
なんちゅうか、いつのまにかマルチメディア(死語)なPCになってしまっているなぁ。
PR
せっかく買ったスピーカーを今更換えるのもなんだし、どうせジャンクにはミニコンのスピーカーばっかりだし…
ということで、長年の懸案だった(大げさ)サウンドカードを増設することにした。
中古コーナーにいつも500円代のから、わりと最近のまで並んでいるのが気になってもいたことだし。
最初にサウンドカードを買おうかなと思ったのは、雑音が気になったときだった。
この時はUSBスピーカー購入で立ち消えに。
次は音楽作成ソフト(DAW)を購入したとき。 一番安いヤツでも充分ということだったけれど、無くてもそれなりに何とかなっていたので、この時も見送り。
というか、サウンドカード出力を使うと、当然スピーカーをどうやって鳴らすか? という問題が出てくるわけで、そこあたりで面倒くさくなってしまった。
そのときは、ラジカセのラインに繋ぐより高音質じゃないと意味がないから、1万円弱のアンプ内蔵スピーカーを買わなきゃいけないかなぁ、光で繋ぐとなるともうすこしかかるかな、とか考えていた。
まず情報収集。
中古に並んでいるのは、たいていが 裸の Sound Blaster 。
ドライバやソフトのサポートを確認してみる。
http://jp.creative.com/support/downloads/
かなり古い製品まで最新のドライバが供給されている模様なので、問題なしと判断。
購入したのは Sound Blaster Audigy (初代無印)
http://jp.creative.com/products/product.asp?category=1&subcategory=205&product=4847&nav=0&listby=brand
ちょっと型番が違うけれどほぼ同等品。 箱に表記されてる対応OSは Windows 98SE/Me/2000 まで!! 思いっきり古い。
発売当時の定価は13,800円。 なにはともあれ金メッキのコネクタがまぶしいぞ。
1700円で購入。 現行の Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX とほぼ同じ値段だから、そっちにすれば何も苦労も問題もないのだけど… なんとなく、最近の流れで中古を使ってみたかった。
あと「オーディオは重厚長大」というのを、未だに引きずっているところがある(苦笑)
でも、最大の決め手は金メッキ!!
インストールCDが付属。 しかしXP対応じゃない…
ちょっと迷ったが、トラブればまた復旧すればいいという気分になっているので、添付CDからインストール。
けっこう時間がかかる。 1時間くらい経ったところで、なにかエラーメッセージが出て止まっている。 USB関係らしかった。 USB2が出る前の製品だからなぁ。
なんとかドライバやソフトが全部入った。 オンラインアップデートなんてのもインストールされてるので、再起動させるとアップデートを求められる。
いろいろと設定を進めていくと、CDからインストールされたモノを全部消して、改めて再インストールしている模様。 やれやれ
ドライバやソフトのダウンロード・インストールで、またかなり待たされる。 CD1枚分を、ネット経由で展開しているようだからなぁ…
夕方から作業始めて、何とか終わったのが深夜だから、全部で6時間くらいかかったのかな。
2000年頃の製品だなぁと思ったのはタスクバーが用意されていたこと。 デスクトップ上部に表示される。
当時の流行だな。 ロータスオフィス2000にも有ったし、グラフィックソフトなどにも用意されていた記憶がある。
付属ソフトやサンプルゲームも動くようだけれど、古い! デモムービーの解像度も低い。
付属の ASIO が、今のDAWと相性が悪く(古すぎて対応してない?)動かない程度で、他はだいたい普通に作動している模様。
一番恩恵を受けたのは DAW だったなぁ。
CPU使用率が100%に張り付いていた重いサンプルデータが、10%ちょっとで動く。
ノイズが大幅に低下。
今のマザーボードはそんなにノイズは大きくなかったけれど、これまでUSBスピーカーのノイズレスに慣れているため、やはりちょっと気になっていた。 おもわず音声スペクトルアナライザーソフト「WaveSpectra」v1.40 で確認しちゃった。 いろいろとざわついていたな。
高速リアルタイム スペクトラムアナライザー WaveSpectra
http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/ws/ws.html
それが、まったくフラットに落ち着いちゃったからビックリ。
そのほか、いろいろと改善される部分が多い。 今までサウンドカード購入を見送ってきたことを後悔する。
肝心の音の方は… ほぼジャンクのスピーカーを100均のケーブルで繋いでいるから、よくわからないw
少なくとも悪くはなっていないようだ。
かなり良くなったような気はしているけれど、ちゃんとした環境ではないからなぁ(笑)
ということで、長年の懸案だった(大げさ)サウンドカードを増設することにした。
中古コーナーにいつも500円代のから、わりと最近のまで並んでいるのが気になってもいたことだし。
最初にサウンドカードを買おうかなと思ったのは、雑音が気になったときだった。
この時はUSBスピーカー購入で立ち消えに。
次は音楽作成ソフト(DAW)を購入したとき。 一番安いヤツでも充分ということだったけれど、無くてもそれなりに何とかなっていたので、この時も見送り。
というか、サウンドカード出力を使うと、当然スピーカーをどうやって鳴らすか? という問題が出てくるわけで、そこあたりで面倒くさくなってしまった。
そのときは、ラジカセのラインに繋ぐより高音質じゃないと意味がないから、1万円弱のアンプ内蔵スピーカーを買わなきゃいけないかなぁ、光で繋ぐとなるともうすこしかかるかな、とか考えていた。
まず情報収集。
中古に並んでいるのは、たいていが 裸の Sound Blaster 。
ドライバやソフトのサポートを確認してみる。
http://jp.creative.com/support/downloads/
かなり古い製品まで最新のドライバが供給されている模様なので、問題なしと判断。
購入したのは Sound Blaster Audigy (初代無印)
http://jp.creative.com/products/product.asp?category=1&subcategory=205&product=4847&nav=0&listby=brand
ちょっと型番が違うけれどほぼ同等品。 箱に表記されてる対応OSは Windows 98SE/Me/2000 まで!! 思いっきり古い。
発売当時の定価は13,800円。 なにはともあれ金メッキのコネクタがまぶしいぞ。
1700円で購入。 現行の Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX とほぼ同じ値段だから、そっちにすれば何も苦労も問題もないのだけど… なんとなく、最近の流れで中古を使ってみたかった。
あと「オーディオは重厚長大」というのを、未だに引きずっているところがある(苦笑)
でも、最大の決め手は金メッキ!!
インストールCDが付属。 しかしXP対応じゃない…
ちょっと迷ったが、トラブればまた復旧すればいいという気分になっているので、添付CDからインストール。
けっこう時間がかかる。 1時間くらい経ったところで、なにかエラーメッセージが出て止まっている。 USB関係らしかった。 USB2が出る前の製品だからなぁ。
なんとかドライバやソフトが全部入った。 オンラインアップデートなんてのもインストールされてるので、再起動させるとアップデートを求められる。
いろいろと設定を進めていくと、CDからインストールされたモノを全部消して、改めて再インストールしている模様。 やれやれ
ドライバやソフトのダウンロード・インストールで、またかなり待たされる。 CD1枚分を、ネット経由で展開しているようだからなぁ…
夕方から作業始めて、何とか終わったのが深夜だから、全部で6時間くらいかかったのかな。
2000年頃の製品だなぁと思ったのはタスクバーが用意されていたこと。 デスクトップ上部に表示される。
当時の流行だな。 ロータスオフィス2000にも有ったし、グラフィックソフトなどにも用意されていた記憶がある。
付属ソフトやサンプルゲームも動くようだけれど、古い! デモムービーの解像度も低い。
付属の ASIO が、今のDAWと相性が悪く(古すぎて対応してない?)動かない程度で、他はだいたい普通に作動している模様。
一番恩恵を受けたのは DAW だったなぁ。
CPU使用率が100%に張り付いていた重いサンプルデータが、10%ちょっとで動く。
ノイズが大幅に低下。
今のマザーボードはそんなにノイズは大きくなかったけれど、これまでUSBスピーカーのノイズレスに慣れているため、やはりちょっと気になっていた。 おもわず音声スペクトルアナライザーソフト「WaveSpectra」v1.40 で確認しちゃった。 いろいろとざわついていたな。
高速リアルタイム スペクトラムアナライザー WaveSpectra
http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/ws/ws.html
それが、まったくフラットに落ち着いちゃったからビックリ。
そのほか、いろいろと改善される部分が多い。 今までサウンドカード購入を見送ってきたことを後悔する。
肝心の音の方は… ほぼジャンクのスピーカーを100均のケーブルで繋いでいるから、よくわからないw
少なくとも悪くはなっていないようだ。
かなり良くなったような気はしているけれど、ちゃんとした環境ではないからなぁ(笑)
XPをクリーンインストールしたけれど、そのわりにパソコンが遅い。
以前の環境と、マザーボード載せ替えのゴタゴタの環境をそのまま引き継いてしまったような気がするぞ。
フリーのソフトであれこれ環境を見直そうとしたが、どうもうまくいかない。
本格的にヤバイと感じたのは、バックグラウンドで何か動いていてCPU使用率が常時50%になってしまったこと。 ドライバの更新などで一時は直ったかと思ったら、翌日また再発していたりする。
それを解消しようと悪戦苦闘。 「窓の手」で設定をいじるが、設定の保存でエラーがでてしまう!!
ここまでこじらせてしまうと、ノートン先生にお願いするしかない。
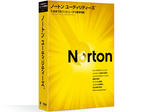
http://www.symantecstore.jp/trial/index.asp
とりあえずノートンユーティリティ体験版をインストール。
「レジストリのクリーニング」を起動させると、なにやら小1時間ほどガリガリとやっている。 700以上の項目を修正していたみたいだ。
「起動の管理」「サービスの管理」「レジストリの断片化解消」「ディスクのクリーニング」「Windowsディスクデフラグ」を順番に実行。
大丈夫かなぁと感じるほど、設定の最適化に時間がかかった。
だいたいは快適、少々軽くなったのだろうな。
この手の、市販のディスク管理ツールを使うのは久しぶり
MacのOSが7.5だった時代にノートンを使っていた。 win95時代には WinProbe 95 というのを使用。
それ以降はオンラインソフト等で、適当にやっている。
起動するたびに、いちいち全スキャンして修復箇所を数個みつけてくるんだけど、正直うざい。 いちいち「修復」するたびに復元ポイントを作ったりする。 その後、保存していた設定が無効になっている部分があるような気がするけど…
本当に仕事オンリーのPCならば常駐させておいてもいいけれど、そうじゃない場合はたまにチェックする程度で充分かなと思った。
いまは単体で4980円程度なんだな。 昔は3倍以上したような記憶があるが…
ついでだから、ノートンインターネットセキュリティの体験版もインストールする。
この種のソフトを、今後購入することがあるだろうかなぁ?
MSがセキュリティソフトを配布しちゃう時代だからなぁ…
今回は体験版を30日使うだけで終わりそうな気がする。
海外を探せば、いろいろフリーのヤツとか体験版が多数有るから、次々に乗り変えていけば、ずっと無料でしのげそうな気がしてくる、今日この頃。
海外の体験版やキャンペーンでフリーのソフト等の情報
Techno360 : http://www.techno360.in/
以前の環境と、マザーボード載せ替えのゴタゴタの環境をそのまま引き継いてしまったような気がするぞ。
フリーのソフトであれこれ環境を見直そうとしたが、どうもうまくいかない。
本格的にヤバイと感じたのは、バックグラウンドで何か動いていてCPU使用率が常時50%になってしまったこと。 ドライバの更新などで一時は直ったかと思ったら、翌日また再発していたりする。
それを解消しようと悪戦苦闘。 「窓の手」で設定をいじるが、設定の保存でエラーがでてしまう!!
ここまでこじらせてしまうと、ノートン先生にお願いするしかない。
http://www.symantecstore.jp/trial/index.asp
とりあえずノートンユーティリティ体験版をインストール。
「レジストリのクリーニング」を起動させると、なにやら小1時間ほどガリガリとやっている。 700以上の項目を修正していたみたいだ。
「起動の管理」「サービスの管理」「レジストリの断片化解消」「ディスクのクリーニング」「Windowsディスクデフラグ」を順番に実行。
大丈夫かなぁと感じるほど、設定の最適化に時間がかかった。
だいたいは快適、少々軽くなったのだろうな。
この手の、市販のディスク管理ツールを使うのは久しぶり
MacのOSが7.5だった時代にノートンを使っていた。 win95時代には WinProbe 95 というのを使用。
それ以降はオンラインソフト等で、適当にやっている。
起動するたびに、いちいち全スキャンして修復箇所を数個みつけてくるんだけど、正直うざい。 いちいち「修復」するたびに復元ポイントを作ったりする。 その後、保存していた設定が無効になっている部分があるような気がするけど…
本当に仕事オンリーのPCならば常駐させておいてもいいけれど、そうじゃない場合はたまにチェックする程度で充分かなと思った。
いまは単体で4980円程度なんだな。 昔は3倍以上したような記憶があるが…
ついでだから、ノートンインターネットセキュリティの体験版もインストールする。
この種のソフトを、今後購入することがあるだろうかなぁ?
MSがセキュリティソフトを配布しちゃう時代だからなぁ…
今回は体験版を30日使うだけで終わりそうな気がする。
海外を探せば、いろいろフリーのヤツとか体験版が多数有るから、次々に乗り変えていけば、ずっと無料でしのげそうな気がしてくる、今日この頃。
海外の体験版やキャンペーンでフリーのソフト等の情報
Techno360 : http://www.techno360.in/
手持ちのパソコン用スピーカーと言えるものは、数えてみれば結構ある。
パソコンに付属していたアンプ無しのものが3個。 アンプ付きが3個(CDプレーヤーとかウォークマンに繋げるために購入したのが2つほど)。 USBスピーカーが1個。
以前のPCで、ちょっとノイズが気になったのでUSBスピーカーを購入。
サンワサプライ:MM-SPU2WH
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-SPU2WH&cate=1&keyword=MM%2DSPU2WH

購入当時はAPPLEのパクリっぽいと感じたな。

2002年の大福iMac
USBスピーカーとしては最廉価のはずだが、けっこう音がいい。 同価格帯のアンプ付きスピーカーよりはいい。 もうちょっと上のクラスと同等以上。 ノイズ無しだし、定位が安定してる。 接続がUSBケーブルだけという手軽さも楽。
ただ、PCで鳴っている音を録音するとき不便。
スピーカーで鳴っている音をPC内部で作っているワケじゃないから、当然のことながら普通の録音ソフトでは録音できない。-
よりいい音で聞きたいときはラジカセにラインで繋ぐけれど、これはこれでディスプレイと離れてるので、DVDを見るときは不自然な感じ。
この際なので、またもやリサイクルショップでスピーカーを物色。
オーム電機のSW-2000を700円で購入。 返品は10日以内。

出力は30w。
型番からすると、2000年頃の製品だろうか?
BOSE 501Z のパチモノ臭さが全開。

1992年頃登場した時は、かなりの評判だったからなぁ。 写真は、後継のAM-10 IV
レベルメーターが光らないと思ってたら、かなりの大音量を入れたら動いた。

イコライザをいじっても、あんまり代わり映えがしないドロ~ンとした音。
いわゆる安物PCスピーカっぽい音が低音まで伸びてるだけ、という印象。
大音量でも破綻しないかわりに、小音量ではおおざっぱにしか聞こえないという感じかな。
ボリュームを手動操作するのは久しぶりだけど(テレビやラジカセはリモコン操作)、やっぱり手っ取り早くていいな。 サブウーファーを手元に置くってのも、ちょっと微妙ではあるけれど。
「アンプ付きサブウーファー」としてだけ使って、スピーカーそのものは別のジャンク(!)に置き換えようかな。
パソコンに付属していたアンプ無しのものが3個。 アンプ付きが3個(CDプレーヤーとかウォークマンに繋げるために購入したのが2つほど)。 USBスピーカーが1個。
以前のPCで、ちょっとノイズが気になったのでUSBスピーカーを購入。
サンワサプライ:MM-SPU2WH
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-SPU2WH&cate=1&keyword=MM%2DSPU2WH
購入当時はAPPLEのパクリっぽいと感じたな。
2002年の大福iMac
USBスピーカーとしては最廉価のはずだが、けっこう音がいい。 同価格帯のアンプ付きスピーカーよりはいい。 もうちょっと上のクラスと同等以上。 ノイズ無しだし、定位が安定してる。 接続がUSBケーブルだけという手軽さも楽。
ただ、PCで鳴っている音を録音するとき不便。
スピーカーで鳴っている音をPC内部で作っているワケじゃないから、当然のことながら普通の録音ソフトでは録音できない。-
よりいい音で聞きたいときはラジカセにラインで繋ぐけれど、これはこれでディスプレイと離れてるので、DVDを見るときは不自然な感じ。
この際なので、またもやリサイクルショップでスピーカーを物色。
オーム電機のSW-2000を700円で購入。 返品は10日以内。
出力は30w。
型番からすると、2000年頃の製品だろうか?
BOSE 501Z のパチモノ臭さが全開。
1992年頃登場した時は、かなりの評判だったからなぁ。 写真は、後継のAM-10 IV
レベルメーターが光らないと思ってたら、かなりの大音量を入れたら動いた。
イコライザをいじっても、あんまり代わり映えがしないドロ~ンとした音。
いわゆる安物PCスピーカっぽい音が低音まで伸びてるだけ、という印象。
大音量でも破綻しないかわりに、小音量ではおおざっぱにしか聞こえないという感じかな。
ボリュームを手動操作するのは久しぶりだけど(テレビやラジカセはリモコン操作)、やっぱり手っ取り早くていいな。 サブウーファーを手元に置くってのも、ちょっと微妙ではあるけれど。
「アンプ付きサブウーファー」としてだけ使って、スピーカーそのものは別のジャンク(!)に置き換えようかな。
ベンチマークソフトであれこれ試しているうちに、ちょっと温度が気になってきたのでケースファンを増設。
せっかくケースにファンコントローラーが付いているのに、使わないのはもったいない、ってのもあるな。
ついでにフィルターも追加してみた。
アイネックス アルミファンフィルター 120mm用(ブラック) CFA-120A-BK
http://www.ainex.jp/products/cfa-a.htm

オウルテック LEDケースファン OWL-Fシリーズ
http://www.owltech.co.jp/products/case_fan/owl/FY/LED_fan/FY_LED.html

価格が倍くらいする「超静音」も有ったけれど、どうせフルパワーで回すものでもないし、もともとケースに付いていた同メーカー品だってうるさいわけでもなかったので、こんなものだろう。
LEDは電源ボタンと同じスカイブルー。
ファンコントローラーを回すと明るさが変わるのが、ちょっと嬉しい。
グラフィックボードは35℃あたりで安定。 ベンチマーク時に40℃を少し超えるくらい。
CPUは50℃~60℃の間で、ケースファン増設前と同じ。 ベンチマークで1時間負荷をかけ続けると70℃を超える。 リテールの限界なのかなぁ。
もしCPUを載せ替えることが有れば、そのときは別途CPUクーラーを用意しようかな。
安いCPUクーラーでもリテールより冷えるだろうし、ファンの回転数が下がることで静かになるだろうから。
ケースが無駄にでかいと思っていたけど、ATXボードを載せ大型CPUクーラーも載せるとなると、やはりこれくらいは必要だったんだな。
せっかくケースにファンコントローラーが付いているのに、使わないのはもったいない、ってのもあるな。
ついでにフィルターも追加してみた。
アイネックス アルミファンフィルター 120mm用(ブラック) CFA-120A-BK
http://www.ainex.jp/products/cfa-a.htm
オウルテック LEDケースファン OWL-Fシリーズ
http://www.owltech.co.jp/products/case_fan/owl/FY/LED_fan/FY_LED.html
価格が倍くらいする「超静音」も有ったけれど、どうせフルパワーで回すものでもないし、もともとケースに付いていた同メーカー品だってうるさいわけでもなかったので、こんなものだろう。
LEDは電源ボタンと同じスカイブルー。
ファンコントローラーを回すと明るさが変わるのが、ちょっと嬉しい。
グラフィックボードは35℃あたりで安定。 ベンチマーク時に40℃を少し超えるくらい。
CPUは50℃~60℃の間で、ケースファン増設前と同じ。 ベンチマークで1時間負荷をかけ続けると70℃を超える。 リテールの限界なのかなぁ。
もしCPUを載せ替えることが有れば、そのときは別途CPUクーラーを用意しようかな。
安いCPUクーラーでもリテールより冷えるだろうし、ファンの回転数が下がることで静かになるだろうから。
ケースが無駄にでかいと思っていたけど、ATXボードを載せ大型CPUクーラーも載せるとなると、やはりこれくらいは必要だったんだな。
